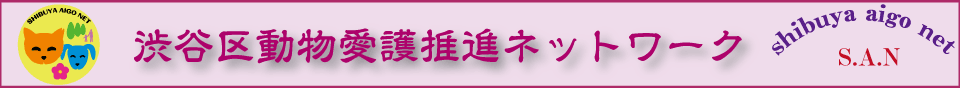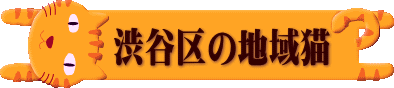🐾地域猫のお役立情報

地域猫-手術済みの印 耳カット
地域猫の手術済の印に何が最適か
- 耳先カットと、ピアス、マイクロチップの長所・短所
- 地域猫の不妊去勢手術済の目印として、渋谷区では耳先カットを行っています。一目で分かりやすい印があれば、地域の人々にも、「手術を受け、世話されている猫」と認知してもらえますし、再度手術のために捕獲することもなくなります。
以前はこうした手術済の印として、耳ピアスや首輪、最近ではマイクロチップを装着する例もありますが、いずれもあまり実用的ではありません。 ここでは、それぞれの方法のメリット、デメリットを挙げてみました。これから地域猫の手術をする方に参考にしていただければと思います。 - 耳先カットを薦める理由
- 耳カット(イヤティッピング)は現在、イギリスをはじめ、世界の先進国で、猫にとって最も安全で、見た目にも分かりやすい方法として、行われています。
「耳を切る」という言葉のせいか、獣医師のような専門家でも「虐待になるのでは」と誤解している人も多いようですが、耳のカットは不妊去勢手術と同時に行うので、動物は痛みを感じません。カットによる出血はありますが、手術中に止血し、翌日元の場所に放すときには完全に止まっています。
デメリットとしては、獣医師によって切り込み方が異なり、切り込みが浅い場合は見た目に分かりにくいということがあります。特にオス猫はケンカでも耳先を切ることがあります。ケンカなどでちぎれた場合と、メスやハサミでカットしたものは違いがありますので、見慣れている人に確認してもらうことが必要です。 - ピアスは外れたり、炎症を起こす危険が!
- 地域猫の不妊去勢手術済の目印として、渋谷区では耳先カットを行っています。一目で分かりやすい印があれば、地域の人々にも、「手術を受け、世話されている猫」と認知してもらえますし、再度手術のために捕獲することもなくなります。
猫の耳にピアスをつけることは、見た目に愛らしく、以前は手術済の印としてよく行われていました。しかし、外れやすいというデメリットがあるため、最近は耳カットに移行してきています。
ピアスの装着は、耳に小さな穴を開け、ビーズを細い糸(テグス)で付けるのですが、早い時は1週間ぐらいで取れてしまいます。逆に強く装着した場合は、穴と糸の摩擦で炎症を起こすことがあり、猫も耳をかきむしるので悪化します。 ビーズを針金で耳に付けた例も見ましたが、ビーズが外れて針金だけが残り、それが耳を傷つけたり、接触した他の猫まで傷つけた例もありました。
もともと猫にとってはピアスは異物であり、装着することはストレスとなるでしょう。 - マイロクチップは非実用的
- 静岡市など一部の自治体では、手術した猫にマイロクチップを装着しています。最近は、飼い犬・飼い猫へのマイロクチップ装着が推奨されていますので、関心も高まっているようです。もちろん飼い犬や飼い猫が迷子になった場合には大変有効ですが、地域の猫たちにはあまり実用的ではないでしょう。
マイロクチップの情報を読み取るには、体にリーダーを当てなければならないため、捕獲してリーダーのある病院などに運ばなければなりません。しかし、手術のために一度捕獲された猫は、大変用心深くなり、捕まりにくくなっていることが多いのです。再度の捕獲は、猫にとって大きなストレスになり、地域猫のボランティアにとっても負担となります。 - イギリスでは以前から耳カット
-
のら猫の「TNR」(捕獲して手術し、元の場所にもどす)活動を20年以上前から行ってきたイキリスでは、この耳カット(イヤ・ティッピング)を最も適切な手術済の識別方法として世界に進めています。世界で最も伝統のある愛護団体「王立動物虐待防止協会(RSPCA)」にもこの方法が認められています。
すなわち、耳カットは決して虐待ではなく、その反対に野良猫の福祉のためであるということが認められているのです。
米国でも、以前は耳に標識をつける方法や、手術跡に青い刺青を残す方法などが行われてきましたが、標識はピアス同様外れやすく、刺青は、毛が伸びてしまうと、猫を捕獲ケージの中に入れても分からないというデメリットがあります。 そこで最近は「野良猫同盟」など多くの愛護団体や獣医師団体が、耳カットの方法を採用しています。 -
 イギリスはじめヨーロッパで広く野良猫の不妊去勢を進めている「SNIPINTERNATIONAL」のサイトでは、耳先カットの利点や方法を獣医師向けに掲載しています。
イギリスはじめヨーロッパで広く野良猫の不妊去勢を進めている「SNIPINTERNATIONAL」のサイトでは、耳先カットの利点や方法を獣医師向けに掲載しています。
日本でも、神奈川捨猫防止会が昨年、獣医師向けの耳カット方法や器具についての説明を、会報と一緒に配りました。
なお、耳先カットの形状として、耳の先端をまっすぐ横に切るところと、タテに切り込みを入れるところがあるようです。
●猫ハウス●
 「猫ハウス」について、お問い合わせがありましたので、写真でご紹介します。
「猫ハウス」について、お問い合わせがありましたので、写真でご紹介します。ネットワーク式の猫ハウスは、段ボールを使った簡単なものです。
発泡スチロールの箱を使用している方も多いと思いますが、
段ボール箱を梱包用プチプチシートでおおって防水加工することで、
保温効果が高くなります。
入り口を上の方に作るのもコツ。
入り口の上に小さい屋根を貼り付けると、なおよいです。
中に暖かい布などを敷きましょう。このハウス、猫たちはけっこう気に入り“入居”しています。
一冬越したら、新しいものに作り替えます。
●外猫用にトイレを作ると便利●
 50センチ×30センチ程度で、材料「ゼオライト」1袋、値段は10リットル 900円位です。 土があれば、10センチ位堀り、そこにゼオライトを入れるだけです。ゼオライトは水はけが良く雨に打たれたり、水を掛けることで匂いがなくなります。
50センチ×30センチ程度で、材料「ゼオライト」1袋、値段は10リットル 900円位です。 土があれば、10センチ位堀り、そこにゼオライトを入れるだけです。ゼオライトは水はけが良く雨に打たれたり、水を掛けることで匂いがなくなります。糞は、はさんでビニール袋にいれて捨ててください。重曹かクエン酸(粉)を適宜撒いてください。 代用品として目地砂も排水性が高く利用価値があります。大きな植え木鉢を利用しても結構です。 猫が落ち着ける場所を選んでください。食事場所と近くでは用を足しません。なるべく距離をあけ、臭いが行かない場所に作って下さい。トイレは清潔に保ち、ぬれていると用は足しません。 (神宮前の猫トイレ)
●猫はよく寝る●

愛猫がぐっすり眠るための条件
- 狭いところ
- 邪魔されることがない、安全で高いところ
- 通気性がよい快適なところ
- 薄暗いところ
安眠できないとイライラして飼い主さんを攻撃することもあります。
●豆知識 ~動物愛護及び管理に関する法律~ ●
第5章 罰則 27条
- 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する
- 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、100万円以下の罰金に処する
- 愛護動物を遺棄した者は、100万円以下の罰金に処する
渋谷区内でも、動物を飼育する人が年々増えてきています。 動物の飼育を通して地域のコミュニケーションが深まる一方で、動物虐待や鳴き声の トラブル、ふん尿などに起因する問題も発生しています。
渋谷区では「人と動物が共生できるまちづくり」をめざして、人と動物が快適に生活するための新しいルールづくりに取り組んでいます。